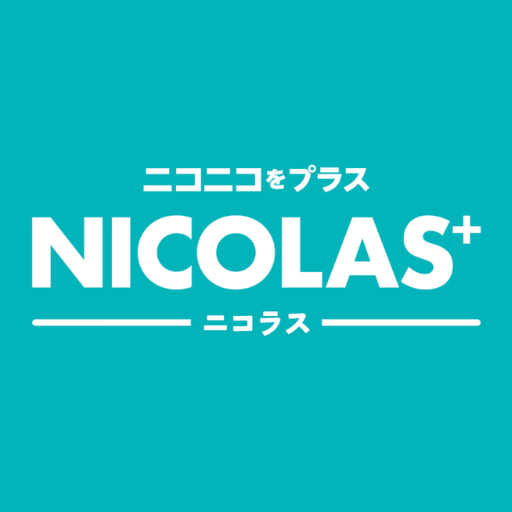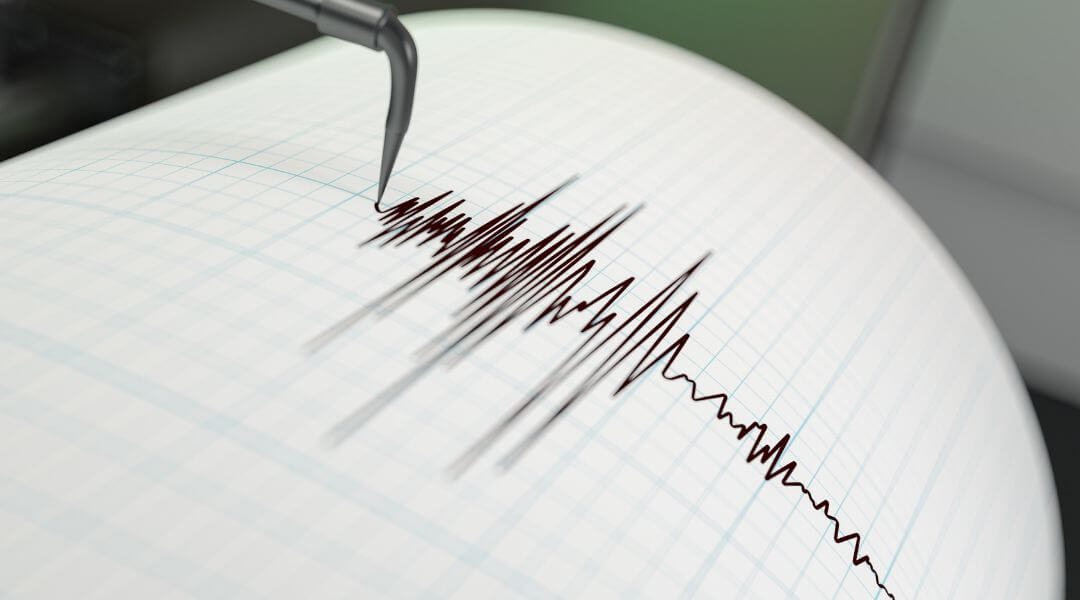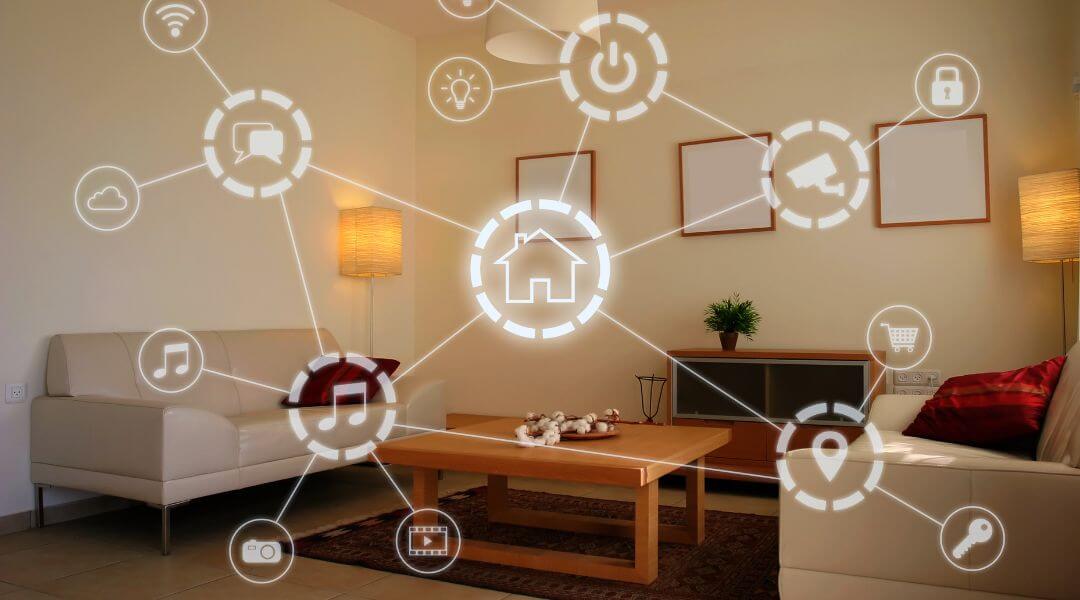災害用の「マンホールトイレ」とは?

「マンホールトイレ」とは、下水道のマンホールを活用して設置する簡易トイレのことです。
東日本大震災や、熊本地震の時にも一部の自治体で使われました。
例えば、大きな地震や台風などの災害が発生した際、水道や電気が止まってしまい、通常のトイレが使えなくなることがあります。
そんな時に、マンホールトイレが活躍します。
マンホールトイレの仕組み
災害時にマンホールの蓋を開けて、その上に専用の便座を設置します。
そして、目隠し用のパーテーションを立ててプライバシーを確保できるようにします。
下水道に直接つながっているので、排泄物はそのまま下水へ流れます。
これによって、衛生的な状態を保ちながらトイレを使うことができるんです。
パッと見だと、ふつうの仮設トイレにも見えますね。
違いは、仮設トイレがタンクに汚物を溜めていくのに対して、マンホールトイレは都度下水に流すことができる点です。
設置されている場所
マンホールトイレは全国で増えてきていて、災害に備えて自治体がマンホールトイレを導入しています。
現在、全国各地でマンホールトイレは自治体によって導入され、
学校や公園など、避難所として指定されている場所にあらかじめ設置されています。
災害時に備えて、地域の住民に使い方を教える訓練が行われている地域もあります。
マンホールトイレのメリット
1. 衛生的、ニオイが少ない
仮設トイレと比べたときに、マンホールトイレが優れている点はまず衛生面です。
仮設トイレだと、排泄物がたまってしまい、臭いや衛生の悪化が懸念されますが、マンホールトイレは下水に直接流すため、臭いが少なく、長期間使用することが可能です。
さらに汲み取り作業も不要。
仮設トイレにありがちな悩みの一つ、「悪臭がしない」というのは、大きなメリットです!
2. 震災後すぐに使える
設置が簡単で、災害直後にすぐ使えるのも大きなメリットです。
3. 段差がない
マンホール部分をそのまま突き上げてトイレにする形なので、段差がなく、高齢の方や障がいを持った方でも簡単に用を足すことができます。
仮設トイレに多い「和式」のトイレも、マンホールトイレにはほとんどなく、洋式が主流です。
4. 長期的に利用可能
長期的な避難生活が必要な場合でも、下水道が機能している限り持続的に使用できます。
デメリットと課題について
理想的な解決策に見えるマンホールトイレですが、デメリットや課題もあります。
1. 下水道が損傷すると使えない
たとえば、地震などで下水道自体が損傷してしまうと、マンホールトイレも使えなくなる可能性があります。
大規模な地震の時にはとくに下水道が損傷する場合が多く、東日本大震災のときには、下水道の仮復旧までになんと平均約1か月かかりました。
2. まだまだ数が足りていない
また、マンホールが設置できる場所が限られているため、避難者が多く集まる避難所などでは、トイレの数が不足する場合もあるかもしれません。
マンホールトイレは災害時におけるトイレ問題を解決する有力な方法ですが、下水道インフラが前提となるため、バックアップ策も必要です。
マンホールトイレが近所にあるという場合でも、やっぱり各家庭で災害用トイレセットを備えておくと安心です!
避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(令和4年4月改定 内閣府)でも、マンホールトイレは他の災害時用トイレ(簡易トイレ、携帯用など)と合わせて使うことが書かれています。